在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」「定住者」で子供を日本に呼べる外国人は良いですが、呼べない外国人「特定技能」「技能実習」も多いと思います。
養子縁組を利用して「留学ビザ」「定住者ビザ」の取得を検討しましょう
![]() 子供が6歳未満と時は「定住者ビザ」6歳以上の時は「留学ビザ」を検討しましょう
子供が6歳未満と時は「定住者ビザ」6歳以上の時は「留学ビザ」を検討しましょう
在留資格「留学」とは
【活動の定義】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
在留資格「留学」というと、大学、専門学校、日本語学校等を想像する方も多いですが、中学校や小学校も対象になります。中学校、小学校は義務教育であり、監護体制がしっかりしていれば入学できる可能性があります。
![]() ポイントは「留学」の資格を取って子供を日本の中学校・小学校に通わせること
ポイントは「留学」の資格を取って子供を日本の中学校・小学校に通わせること
a
中学校、小学校に入学する場合の在留資格「留学」の取得手続き
【必要書類】
①監護するに至った経緯、監護計画を説明する資料
②監護人と申請人の関係を立証する資料
③宿泊施設の概要を明らかにする資料
④生活指導担当者の在職証明書
もちろんこれ以外にも必要ですが、注すべき点は監護人、監護計画といった監護に関することです。
つまり監護体制がしっかりしていれば、在留資格を取得できる可能性があります。
![]() ポイントは監護体制
ポイントは監護体制
a
監護体制強化の為の養子縁組
外国の方だけでは監護体制が万全とは言えないケースが大半だと思います。そのような場合に日本人等で生計がしっかりしている方と養子縁組を組むなどして、監護体制を強化することが考えられます
a
日本人と外国人の養子縁組
日本人を養子にするのは日本法に従えばよいというのは当然ですが、外国人を養子にする場合は、国際私法(通称:通則法)という法律に基づいて行います
通則法31条(養子縁組の準拠法)
養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
上記の通り養子縁組の問題はすべて養親の本国法によりますので、養親が日本人の場合は養子の国籍が何であろうと日本の法律に基づきます。
ただ条文の後半に条件が付け加えられており、これを保護要件(セーフガード条項)と呼んでいます。養子の本国法が養子を保護するための要件を求めているときは、それに応じた第三者や公的機関の許可等を備える必要があります。
通則法34条(手続き)
1 親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
養親が日本人で日本で養子縁組をする場合は、日本法に則って行えば問題ありません
![]() 養子縁組は日本の法律に則てやれば問題ありません。ただ養子の本国法の保護要件を満たす必要があります
養子縁組は日本の法律に則てやれば問題ありません。ただ養子の本国法の保護要件を満たす必要があります
![]() 養子縁組で日本国籍は取得できません。帰化が必要です
養子縁組で日本国籍は取得できません。帰化が必要です
在留資格「定住者」で呼ぶ場合
外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合は定住者の在留資格で呼ぶことができます
![]() 外国人の子供が6歳未満の場合は養子縁組をして定住者で呼ぶことができます
外国人の子供が6歳未満の場合は養子縁組をして定住者で呼ぶことができます
a
外国人の子どもの公立学校への受入について(文部科学省HPより)
- 外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受入れる。
- 教科書の無償配付及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障する。
あ
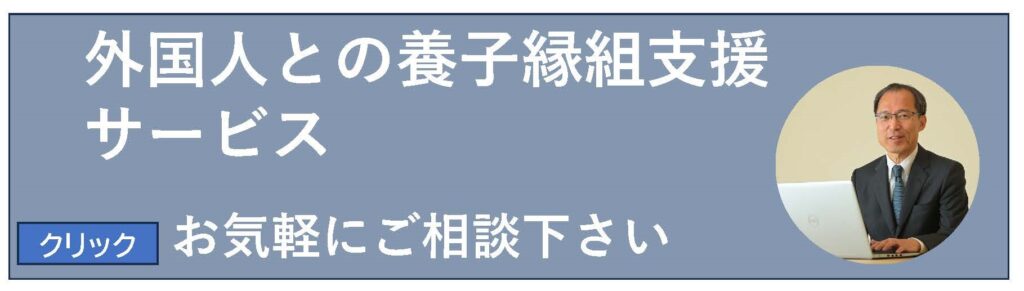
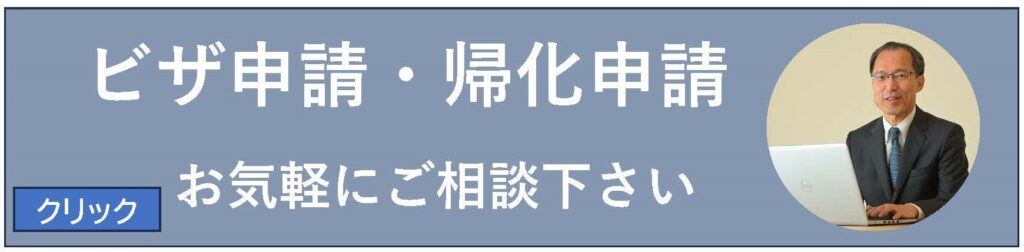

 04-7197-7922
04-7197-7922